年初からナスダックを中心に米国株は下落を続けていますね。まあこういう時もあります。コロナ禍の暴落に比べればまだ屁でもないでしょう。とはいえ、毎朝起きると資産が減っているのはしんどいですよね。
さて、株式の理論価値を単純化すると
株価=将来利益 / 割引率
となります。
いま株価が落ちているのは教科書通りの動きと言えます。なぜなら、米長期金利が上昇しているからです。以下は年初から1月19日現在までの米10年債利回りの推移です。

(CNBC)
金利が上がれば、企業の将来利益を割り引く利率も高くなり、理論株価が下がります。株価は理論通りに下がっています。
なぜ金利は上がっているのか?
長期金利の変動要因は一概に言えるものではありませんが、FRBが金融引き締めのタカ派に変貌していることが一番の要因でしょう。
FRBがタカ派に傾いているのは物価上昇が止まる気配が見られないからです。すべてはインフレ次第と言えるかもしれません。
期待インフレ率の上昇が金利を押し上げ、株価の上値を重くしている状態です。
しかし、インフレは悪いことばかりではありません。アメリカでは15ドルの定食が20ドルに値上がりしていると聞きます。そうやってコストを売値に転嫁できれば企業の利益は増加します。少なくとも名目では。
株価=将来利益 / 割引率
↑
インフレは分母の割引率を押し上げますが、同時に分子の将来利益も押し上げます。分母も分子もどちらも10%上昇したら、理論株価は変わりません。金利と企業業績の綱引きということです。
しかし、今株価が下がっているのが現実なわけですが、それはマーケットはインフレに伴う企業利益の上昇を楽観的には織り込まないからです。今は分母の割引率の上昇という悪い情報だけに反応しています。
ネガティブなニュースは保守的に前もって織り込む。ポジティブなニュースは後でゆっくり織り込む。マーケットはそんな慎重なところがあります。私たちもマーケットの構成員の一人ですが、その気持ちわかりますよね。
前もって織り込むというか、そもそも現実問題として金利は上がっているわけだから、マーケットはその事実を冷静に株価に反映させているだけとも言えます。
これから何度かの決算発表を経て、おそらく各企業のEPSは成長していることが確認できるでしょう。利益率が改善しているかはわかりませんが、少なくとも名目利益は増えているはずです。全体としては。
「株価=将来利益 / 割引率 」の分子の利益部分もインフレで上昇していることをきちんと決算リリースで確認し、マーケットは落ち着きを取り戻していくと思います。
株式は長期ではインフレに負けないです。ただし、短期ではインフレに負ける性質があります。それはシーゲル先生も言っていることです。
株は短期ではインフレヘッジにならない。理由としてよく言われるのは、インフレの結果起きる高金利。債券の利回りが上がり、株と競合し、債券にお金が流れる。株式の利回りが、ある程度債券利回りに見合う程度に上昇するまで株価が急落する。
『シーゲル博士の株式長期投資のすすめ』より抜粋
今はまだ「短期」のフェーズです。割引率の上昇だけに反応しているフェーズ。
株式はペーパーアセットではなく、根源的には実物資産です。インフレでモノの価格が上がれば、その請求権たる株式の価格つまり株価も上がります。
インフレで株式の価値が上がるとまでは言えませんが、少なくとも価格は上がります。
そんな理論通りに動くほどマーケットは甘いものではありませんが、でも今のところは非常に教科書的な値動きですよね。グロースが沈んでますし。
こういう時に大事なのはとにかく強い企業に投資しておくことだと思います。賃金上昇などのコスト増を容易に売値に転嫁できる企業です。
たとえば、マイクロソフトやアドビなんてどうでしょうか。Microsoft365を5%値上げすると宣告されて、解約する企業が果たしてどれだけあるでしょうか。
だから私は安易にバリュー株にポートフォリオを入れ替えるのは反対なんです。こういう時こそPERちょい高めの強い企業を持っていた方が安全と思うんですよね。
赤字の成長企業やPER3桁の企業、所謂ハイパーグロース株は止めといた方がいいと思いますが。


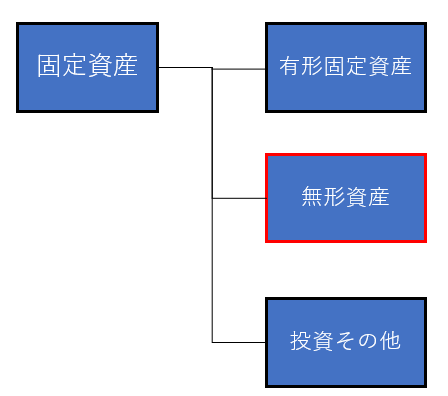



こんばんは。いつも有益な記事をありがとうございます!
勉強していて為替がいまいち腑に落ちない部分があります。
インフレは通貨の価値が下がると思っていたのですが(トルコとかそのようなイメージ)、ドルはインフレが高まってるにも関わらず、なぜどんどんドル高になっているのでしょうか?
日本→デフレでアメリカ→高インフレだと円高ドル安方向になると思っていたのですが、、、
何故か分からずモヤモヤしてしまっていて、お時間あればご教授頂けると幸いです。
こんばんは。
わかります、物価上昇の格差を考えると円高ドル安を想定しちゃいますよね。同感です。
ただ、目先はアメリカは金融正常化で金利が上がっているのでドルに資金が向かうのは自然とも思います。
コロナ禍もあって観光需要も乏しいですし、日本は経済低成長でビジネス投資需要も薄く、これだけ資産価格に差があってもなかなか海外資金を引き寄せないのでしょうかね。
今のドル円相場の妥当性はよくわからないです。
長期的には物価差を反映して円高ドル安になるのではと予測していますが、自信はありません。
今のインフレって、コストプッシュ型、つまりサプライサイドの問題ですよね。
小売売上高が低迷したにも関わらず、CPI上昇が止まらない事がそれを示しています。
素朴な疑問なのですが、この場合、利上げする事に意味はあるんでしょうか?
企業物価を消費者物価に転換した時、需要がそれに耐えられるのか。ここが不安なのです。
ちなみに、我が日本ではこれが全く出来ていない。国家レベルでワイドモードがないw
その代償は株主が負担する事になります。
EPSと割引率の綱引き勝負は、ここが分水嶺になると思います。
日本の僅かなインフレはコストプッシュ型かもしれませんが、アメリカのインフレは違うと思います。
財政刺激等で需要が増大している、高圧経済がインフレの一因です。
供給側だけでなくカネ余りの需要側もインフレの一因であれば、利上げに一定のインフレ抑制効果はあるものと思われます。
こんばんは。いつも記事拝見してます。引き続き応援しております。
0.25%利上げを年4回やっても計1%であり、現状のインフレ率には到底及ばず今後急ピッチな利上げが起こるのではと懸念してます。その場合、将来的には記載されてる様に株価はインフレ分も吸収していくと思ってますが、そこに至る過程はハードな道程になるかもしれないと。ちょっと悲観的ですかね(笑)
こんばんは。
いつもお世話になります。
利上げペースは想定以上のスピードになる可能性がありますよね。
一方で、米長期金利は上昇に一服感が出てきており、債券投資家が何を思っているのか興味があります。
おっしゃる通り、株式は長期的にはインフレを吸収しますが、その道程は困難なのは歴史が示しています。
でもだからこそ株式のリスクプレミアムが高まって、マーケットで生き残った人に大きな利益が与えられるかもしれませんね!